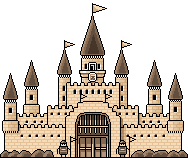<ぶらり福岡>
福岡と博多の違いは?
屋台が並ぶことで有名な那珂川沿い。
この川をはさんで東側を「博多」、西側を「福岡」と呼ぶことがあります。
これは、かつて商人の町・博多と武士の町・福岡に分かれていたからです。
福岡市のことを「博多」と呼ぶのも、中世から「博多」という名前が認識されていたことや、
山陽新幹線の終着駅が「博多駅」であり、
ビジネスマンたちが福岡へ出張することを「博多に行く」と言うなど、
「博多」という名前が浸透していたことによります。
「福岡」の名は、江戸時代に現在の中央区に福岡城が築かれたときに付けられました。
1889年には、福岡市にするか、博多市にするか議会で議論されたこともありますが、
わずか1票差で福岡市となったエピソードも。
福岡と博多を合わせて「福博」と呼ぶこともあります。
「福博であい橋」
武士のまち「福岡」と商人のまち「博多」が出会う場所ということで、
「福博であい橋」と命名されたそうです。
   
左から 博多ラーメン(一蘭)、どん麺、クエ鍋、イカ造り(呼子)
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

櫛田神社 |
博多の総鎮守として、「お櫛田さん」
の愛称で広く市民から親しまれている神社。
境内の入り口付近には「櫛田の銀杏」
と呼ばれる樹齢約1000年の銀杏の木がそびえる

櫛田の銀杏 |

ふるさと館 |
櫛田神社向かいの「博多町家」ふるさと館。
ここは明治・大正時代の博多の
暮らしと文化を楽しく紹介する施設。
明治時代の町家を移築。

博多壁 |

貴賓館(天神中央公園) |
数少ない明治時代のフレンチルネッサンス
を基調とする木造公共建物。
国の重要文化財に指定され保存。

福博であい橋の中洲側たもとに立つ
三人舞妓銅像 |

福岡城跡 |
初代福岡藩主・黒田長政が、
慶長6年(1601)から7年がかりで築城。
平山城で、大中小の各天守台
と約50の櫓があった。別名「舞鶴城」

下之橋御門と(伝)潮見櫓
|

福岡城(大天守台)跡 |
福岡城には天守閣がもともと
建設されなかったとされていますが、
「はじめは天守閣が建設されたが、
後年取り壊されたのではないか」
とも言われています。
 |